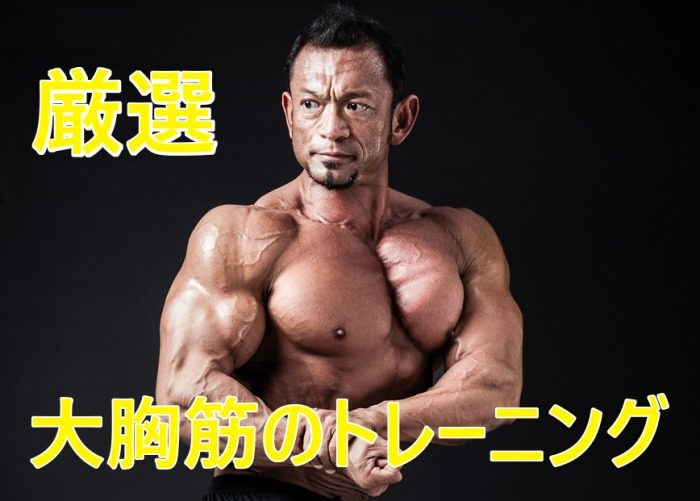
大胸筋を鍛えることで、正面から見た場合に厚い綺麗な胸板を手に入れることができ、男らしい逞しい身体を作ることができます。
ボディメイク・ダイエットにおいて、上半身は下半身に比べて、成果が目に見えやすく継続しやすいと言う点からオススメです。
ここでは、そんな筋肉の中でも大きな大胸筋を鍛えるおすすめの筋トレメニューを厳選して紹介していきます。
 ジンガー
ジンガー
目次
- 1 胸を形成する大胸筋の種類
- 2 大胸筋を鍛えるの王道のトレーニング「ベンチプレス」
- 3 大胸筋上部を鍛える「インクラインベンチプレス」
- 4 大胸筋の下部を鍛える「デクラインベンチプレス」
- 5 大胸筋中部を鍛える「ダンベルベンチプレス」
- 6 大胸筋上部を鍛える「インクラインダンベルプレス・フライ」
- 7 大胸筋下部を鍛える「デクラインダンベルベンチプレス」
- 8 フライ系の種目の王道「ダンベルフライ」
- 9 大胸筋下部を鍛える「ディップス」
- 10 大胸筋上部を鍛える「ダンベル・プルオーバー」
- 11 大胸筋を集中的に強化できる「ケーブルクロスオーバー」
- 12 大胸筋を満遍なく鍛える「チェストプレス」
- 13 大胸筋をしっかりとストレッチできる「バタフライ」
- 14 自宅でできる大胸筋トレ「腕立て伏せ」
- 15 僕が行っている大胸筋の筋トレメニュー
- 16 まとめ
胸を形成する大胸筋の種類
胸を形成する筋肉は大胸筋と言われる強力な筋肉で、腕を横から振る動作の主力筋肉です。上腕を内側に捻る働きもあります。
大胸筋は、1つの筋肉ではありますが、
- 上部(鎖骨部)
- 中部(胸肋部)
- 下部(腹部)
で作用する方向が異なるため、力のかかる方向が異なる種目を選択し、大胸筋を満遍なくトレーニングする必要があります。
初心者の人はそこまで深くは気にすることはないですが、中級者以上の人ならそれぞれの筋肉へアプローチした種目を選んでトレーニングをした方がより大胸筋を発達することができるはずです。
ではそれぞれ紹介していきますね!
大胸筋を鍛えるの王道のトレーニング「ベンチプレス」
- 平らなベンチ台の上に仰向けになりお尻・肩・後頭部をしっかり台につけ、足もはしっかり床につけます。
- 肩甲骨をしっかりと寄せて胸をしっかりストレッチさせます。
- 肩幅の1.5倍程度の広さでバーを握りラックから外します。
- 胸を張った状態でバーベルを胸のトップ目掛けてゆっくりと下ろします。
- 胸を張り、肩甲骨を寄せたままバーベルを持ち上げます。
ベンチプレスの特徴や注意点
ベンチプレスは大胸筋の代表的な多関節種目です。主に大胸筋中部に負荷をかけることができます。トレーニングのBIG3の種目の1つでもあります。
ベンチプレスでは大胸筋と同時に三角筋前部、上腕三頭筋にも負荷を書けることができるので上半身のボディメイクにオススメです。
注意点はバーベルは上げる以上にしっかりと下ろして胸部へストレッチをかけることが大切です。
切り替えしの際に胸でバーベルをバウンドさせてしまったり、お尻を浮かせてしまうと大胸筋への負荷が低くなるので注意してください。
大胸筋上部を鍛える「インクラインベンチプレス」
大胸筋上部の発達に効果的なのがインクラインベンチプレスです。
ベンチ台を30~45度の角度にし、身体を斜め上に傾けて動作を行っていきます。
インクライン種目は大胸筋上部や、肩の前部の発達に欠かせないため、Tシャツを着た上からでも良い身体と分かる、
Tシャツから覗く大胸筋の谷間を作るのにも、インクライン種目は必須と言えます。
大胸筋の下部を鍛える「デクラインベンチプレス」
身体を斜め下に向けて角度を付けて行うのがデクラインベンチプレスです。大胸筋の下部に負荷をかけることができます。
ベンチ台を斜め下へ30~45度の角度にし、身体を斜め上に傾けて動作を行っていきます。(斜め下へ角度が付けられない場合には、足を床ではなくベンチ台に乗せ、お尻を浮かせた状態で行います)
大胸筋下部への刺激を強く入れることが出来るので、腹筋との境目を作ることに効果的で、分厚い胸板を手に入れることができます。
大胸筋中部を鍛える「ダンベルベンチプレス」
- ダンベルをかかえながら平らなベンチ台の上に仰向けになりお尻・肩・後頭部をしっかり台につけ、足もはしっかり床につけます。
- 肩甲骨をしっかりと寄せて胸をしっかりストレッチさせます。
- 手首を真っ直ぐにして、しっかりと肩甲骨をよせ腕を広げ胸を開きます。この時ダンベルは、胸の高さ脇の下に位置させます。
- 腕を床に対して垂直になるように、ダンベルを上へ押し上げます。肘の上に常にダンベルが来るようにしましょう。
- トップの位置まで来たら、ゆっくりと開始位置へと戻して行きます。
ダンベルベンチプレスの特徴や注意点
ダンベルベンチプレスは、バーベルの代わりにダンベルを使用して行う大胸筋の多関節種目です。主に大胸筋中部に負荷をかけることができます。
ベンチプレスと同様に大胸筋と同時に三角筋前部、上腕三頭筋にも負荷を書けることができます。
扱える重量がベンチプレスに比べて90%程度落ちますが、その分肘を深く下げる事が出来るため、大胸筋により強いストレッチをかけることができます。
ちなみ、上記のダンベルベンチプレスを行っているのは、日本で唯一ボディビルのプロとして世界で活躍している山岸秀匡選手です。
山岸秀匡選手の動画どれを見ても参考になるので、筋トレをしている人は一度目を通しておくことをオススメします。
大胸筋上部を鍛える「インクラインダンベルプレス・フライ」
大胸筋上部の発達に効果的なのがインクラインダンベルプレス・フライです。
ベンチ台を30~45度の角度にし、身体を斜め上に傾けて動作を行っていきます。
形の良い大胸筋を作るためには必須の種目です。
大胸筋下部を鍛える「デクラインダンベルベンチプレス」
身体を斜め下に向けて角度を付けて行うのがデクラインダンベルベンチプレスです。こちらは大胸筋下部を刺激できる種目です。
ベンチ台を斜め下へ30~45度の角度にし、身体を斜め上に傾けて動作を行っていきます。(斜め下へ角度が付けられない場合には、足を床ではなくベンチ台に乗せ、お尻を浮かせた状態で行います)
手の平を内側に向けた状態でのトレーニングも可能です
フライ系の種目の王道「ダンベルフライ」
- ダンベルを抱えながらベンチ台に横になります。
- 後頭部、肩、お尻をしっかりとベンチ台に付け、足の裏でしっかりと床に踏ん張ります。
- 腕を床に対して垂直にし、肘を軽く曲げダンベル同士を向かい合わた状態でトップの位置からスタートします。
- 腕が床に平行になるまで、半円を描きながら、ゆっくりとダンベルを持った腕を横に広げていきます。その時、肘の角度は固定しておきます。
- ボトムの位置まで来たら、ゆっくりと開始位置へと戻して行きます。
ダンベルフライの特徴と注意点
ダンベルフライはベンチプレス、ダンベルベンチプレスなどのプレス系の他にフライ系種目の1つです。
こちらは胸にピンポイントで刺激を入れる事が出来る、またプレス系よりもストレッチ(筋肉を伸ばすこと)するので、プレス系よりも重量を下げても刺激を入れることができるので安全面でも優れています。
フライ系の種目は、胸だけに刺激が入ることから、プレス系種目を終えて上腕三頭筋が披露していても胸を追い込めるといったメリットもあります。
プレス系種目と合わせて行うとより効果的です。
ダンベルフライの注意点として、肘を伸ばしきらないということです。
肘を伸ばしきってしまうと大胸筋への刺激が弱くなり、効きが浅くなってしまいます。
なので、肘は少し曲げた状態を維持するようにしてください。
大胸筋下部を鍛える「ディップス」
- 可能な場合にはグリップを広くセットして握ります。
- 上体を前傾したまま肘を90度まで曲げて上体を深く沈めます。
- 脇を締めたまま、両肘を伸ばして上体を持ち上げます。
ディップスの特徴や注意点
ディップスは上半身のスクワットとも呼ばれる多関節種目で、大胸筋下部と合わせて上腕三頭筋も合わせてトレーニングすることができます。
基本的には自分の体重を負荷として行う種目です。
注意点は、上体を上げる際に、肩がすくんだり、脇が開くと負荷が逃げてしまうので注意してください。
また、ディップスを自重でできない人は、マシンディップスなら補助版に脚を乗せて負荷を軽くすることも可能です。
逆に自重じゃ軽すぎるという人は、ディッピングベルトを使用することで負荷を上げることもできます。
ディッピングベルトは懸垂などでも使えるので、これからガッツリ鍛えていくのであれば、持っていて損はない筋トレ器具の1つです。
ディップスは自宅でも椅子があればできる種目なので、腕立て伏せと組み合わせればより効率よく大胸筋を鍛えることができるはずですよー。
大胸筋上部を鍛える「ダンベル・プルオーバー」
- ダンベルを持ちベンチ台に対して垂直で、肩と背中の上部が付くように仰向けになります。
- ダンベルを後方に下ろします。
- 両腕を伸ばしたまま、振り上げるようにダンベルを胸の上まで持ち上げます。
- あとはゆっくり元に位置に戻します。
ダンベル・プルオーバーの特徴や注意点
ダンベル・プルオーバーは、大胸筋上部と、特に上腕三頭筋をターゲットにしたトレーニング種目です。
胸筋の縦への刺激を入れることができる種目で、胸部が延びるので大胸筋上部の筋肥大にも有効です。
注意点は、ダンベルを頭上で扱うためフォーム・動作が安定するまで安全に行える負荷でトレーニングを行っていきましょう。
また特に肩関節が緩い方は注意して行ってください。
大胸筋を集中的に強化できる「ケーブルクロスオーバー」
- 左右のケーブルを高い位置にセットしてグリップを握ります。
- 状態を倒し肩甲骨を寄せ、90度に曲げた肘を両肩の高さまで引き上げます。
- 胸を貼って肩甲骨を寄せたまま、半円を描くようにゆっくりと両手が付く手前まで左右のケーブルを引き寄せます。
- その位置で軽く止め、ゆっくりと戻ります。
ケーブルクロスオーバーの特徴・注意点
ケーブルクロスオーバーは、大胸筋を集中的に強化できる種目です。ケーブルを使用し行うため負荷が常に抜けることがないのが長所です。
特に大胸筋が収縮した時に強い負荷をかけることができ、大胸筋の他、三角筋前部にも刺激を入れることができます。
バリエーションとして、身体を前傾させずまっすぐにたった状態で、特に大胸筋下部に負荷を強く入れることも可能です。
また片手ずつ行うことも可能です。
大胸筋を満遍なく鍛える「チェストプレス」
- バーを握り胸を張って肩甲骨を寄せます。
- 胸を張り肩甲骨を寄せたままバーを押し出しますが、肘がロックしないようにします。
- あとは繰り返しです。
チェストプレスの特徴や注意点
注意点は、大胸筋への刺激を逃げないようにしつつ、怪我を避けるために動作中は肩をベンチに付けて行います。また前に押す際には腰を反らないようにします。
また、バーを深くセットすると大胸筋が強く伸び筋肥大効果も高められます。
グリップを狭くすると三角筋と胸の内側に、グリップを広くすると胸の外側に負荷が強くかかります。
ただし、セットポジションの段階で、肩甲骨を開いてしまうと胸ではなく三角筋前部に負荷がかかるので注意してください。
初心者に特にオススメの種目です。
大胸筋をしっかりとストレッチできる「バタフライ」
- グリップを握った時に、上体と床が平行になるようにマシンを調整します。
- 背中をシートに付け胸をしっかりと張ります。
- 背中と肘を押し当てたまま肘で押します。
- 押した位置で少し止め、ゆっくりと開始位置まで戻ります。
バタフライの特徴や注意点
バタフライは、ダンベルフライと同様に、大胸筋をしっかりとストレッチすることが出来る種目です。
マシンで軌道が一定のため安全に重量を上げていくことが可能です。
三角筋前部も合わせてトレーニングすることができます。
注意点として、最後までしっかりと胸を収縮させることです。
中途半端に止めてしまうと、大胸筋に全く効きませんので。
自宅でできる大胸筋トレ「腕立て伏せ」
- 両手を肩幅より広く付き脇を開いて上体を深く沈めます。
- 胸部のストレッチをしっかりと感じながら全身を一直線になるようにします。
- 全身を一直線に保ちながら、肩からオ上体を持ち上げます。
腕立て伏せの特徴や注意点
腕立て伏せは、場所を選ばずどこでも行うことが出来る大胸筋のトレーニング種目です。
手の幅を狭くすればするほど、上腕三頭筋に負荷がかかります。
器具を何も使わないシンプルな種目ですが手の幅や位置を変えることで、さまざまなバリエーションがあります。
注意点は動作中、お尻が落ちたり、上体が曲がると大胸筋への負荷が弱くなるので、しっかりと体勢を維持することを意識して行ってください。
僕が行っている大胸筋の筋トレメニュー
ちなみに参考までに今ボクが行っている大胸筋のメニューを紹介します。
ずっと同じメニューではないので、多少の変わることもありますが、基本的にこの4種目です。
- ベンチプレス→4~5セット
- インクラインベンチプレス(スミス)→3~4セット
- ペックデック(バタフライ)→2セット
- ディップス→3セット
基本的にはこの4種目ですが、ケーブルを用いたケーブルクロスなどを行う場合もあります。
ベンチプレスとインクラインベンチプレスは重量をなるべく追いたいので、レップ数は少なめです。
ペックデック(バタフライ)やディップスは、結構ハイレップで行うことが多いです。
まとめ
厚い、綺麗な胸板を手に入れたい!男性なら誰しもが1度は考えたことはあるはずです。
胸は背中や脚と比べて服を着た際に外からでも分かりやすいため周りに変化を気付いてもらいやすい部位です。
厚さだけではなくて綺麗な形の大胸筋を作るためにも、いろいろな角度から負荷をかけて満遍なく大胸筋へ負荷を与えることが大切です。
是非、大胸筋トレーニングの参考にしてください。
 ジンガー
ジンガー



コメントを残す